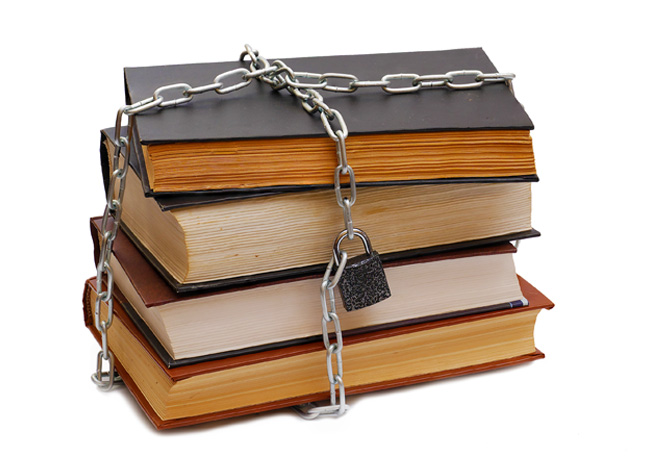
金融庁が検査マニュアル廃止、今後の方針を公表
金融庁は金融庁検査マニュアルの廃止の対応について、進捗状況と今後の課題について公表した。金融庁検査マニュアルは昨年6月に廃止する方針を公表しており、2019年12月には廃止する予定となっている。金融庁検査マニュアルを取り巻く環境や金融庁としての考え方を改めて説明し、各金融機関・業界団体と議論した内容、今後の課題と方針について公表した。今後の取り組みとしては、各金融機関、業界団体、公認会計士協会、日本銀行らをメンバーとした実務レベルの会議を開催し、新たな課題などを議論していくとした。
金融庁検査マニュアルは、バブル崩壊時において不良債権に対応する金融機関へ向け、実施債務超過かどうかを重視した厳格な自己査定・償却・引当ができるように策定されたもの。当時、金融庁としては、バブル崩壊によって発生した不良債権を的確に把握し、足元までの資産価格の下落という要因を引当に反映させ、国内外の信用を回復させることが優先的な課題の1つでもあった。しかし、現在、金融機関の融資を取り巻く環境としては、人口減少、高齢化の進展、産業構造の変化により、借り手の本業の経営悪化の要因が多様化していることに加え、低金利環境の長期化に伴い、厳しい収益環境に置かれている。そのため、金融機関の資業務では自社の強みや個性を活かした取り組みが広がりつつある。
今回、金融庁は、検査マニュアルがこうした金融機関の取り組みを制約し、調整コストや時間を消費していると各業界から多数指摘されているとし、「融資業務は必ずマニュアル通りに行う必要はない。ただ金融機関にとっては、マニュアルに記載されていない事例においては、やりにくい部分が多くあった。結果的に将来を見据えた引当の見積もりよりも、足元のバランスシートを重視した融資が定着している」と語り、「金融検査マニュアルに基づいた引当を否定するつもりはない。ただ足下や将来の情報に基づき、より的確な引当と早期支援を可能にしていきたい」としている。現状、金融庁としては「検査マニュアル廃止後の融資に関する検査・監督の考え方と進め方」というディスカッション・ペーパーと公表しており、すでにこのペーパーに沿った融資を展開・検討している金融機関と議論を進めている。具体的には、地方銀行や公認会計士協会が連携して外部の共通データベース(CRITS、SDB)の情報を利用した引当の見積もりについて検討している。
課題としては、すでに同ペーパーに沿った引当事例の蓄積や関係者間での認識の共通化としているが、他にも融資の幅が広がることで、健全性・適切性についても各業界側から多く指摘されている。マニュアル廃止の結果、より本来的なリスク・将来性を適切に把握されることが期待されているが、態勢の整備にはまだ多くの時間が必要とされている。
2019.09.27